ホロラボ Advent Calendar 2024の8日目です!
最終的に全3回になったので、それぞれのリンクを追記しました!
組織開発のラボとしてのホロラボ
今回は、このシリーズでは初となる人・組織に関わるテーマとなります。
テーマを担当するのは、業務委託の人事としてホロラボに関わってきたみやけんです。
宮﨑健輔、略してみやけんと呼んでもらっています。
さて、このブログですが私が欠席していた経営会議で決まっていまして、蓋を開けたら「組織開発のラボとしてのホロラボ」という最初のお題をもらいました。
最初は「ふむふむ、あんなことこんなこと書こうかな」と思っていたのですが、あまりにも広大なテーマなので、何度かに分解して書かなければならなそうです。
まず今回は私がJoinした2020年のお話、コミュニティ文化が多く残っていたころのお話から始めたいと思います。それ以前についてはCo-Founderである中村薫さん、伊藤タケセンさんがいつか書いてくれるはず(勝手なこと言うw)。
さて、その前に組織というのはかなり壮大なテーマ且つ、どうしても個々人の視点や考えが入りがちな分野ですので、前提を揃えておきます。
組織とは?
ある目的を目指し、幾つかの物とか何人かの人とかで形作られる、秩序のある全体。そういう全体としてのまとまりを作ること。また、その組み立て方。
参照:Oxford Languages
組織開発とは?
一般的には「組織(チーム)を円滑にwork(機能)させるための意図的な働きかけ(介入)※」と定義されます。そして、組織開発の専門家と言われる人々が連想するのは、組織内の対話・ワークショップという手法でしょう。ただそうすると、人事制度などが含まれませんし、このブログでは人事制度などの仕組みづくりも含め広義に「意図的な働きかけ(介入)」としたいと思います。
つまり、組織に対して何かしら働きかけたら、すべて組織開発とします。これで広く何でも話せるようになりました。w
参照:中原 淳・中村 和彦 著『「組織開発の探究」――理論に学び、実践に活かす』ダイヤモンド社. (ちなみにこの書籍自体は組織における対話・ワークショップの歴史と展望をまとめたものです。)
ホロラボの発端
では初めにホロラボが設立された当時の事をお話ししましょう。これを仮に初期Versionと呼んでみましょう。
ホロラボ初期Versionの前身はXRエンジニアのコミュニティです。HP(ヒューレットアンドパッカード)やAppleがガレージで始まったのは有名ですが、ホロラボはコミュニティから始まります。
XRが大好きで、自費でホロレンズを購入し開発をしていたエンジニアのコミュニティが元にあるのです。
ここで出会った中村薫さん、伊藤タケセンさんと、複数のメンバーで出資し合い株式会社ホロラボを立ち上げました。2017年のことです。
この「エンジニアコミュニティが出自である」ということが初期ホロラボにおける大事なポイントになります。

2020年頃のホロラボの組織
では、私がJoinした2020年頃のホロラボはどんな状態だったでしょうか?
いくつかの観点から見ていきましょう。
当時のMission、Vision「みたいなもの」
『HoloLabは、リアルとバーチャルをつなげ、新しいコンピューティングのスタイルや表現、体験を生み出すためのノウハウを広く世の中に提案し続けます。』
(2024年12月8日現時点ではまだホームページのトップに掲載されています。)
明確にMission、Visionと表現されていたわけではありません。むしろ取締役2名は、Mission、Visionのような「いわゆる大きく目指すもの」を設定することを忌避していました。この明確な「Mission、Vision」の提示を避けていたことに一つの初期の文化的特徴が表れています。(これについてもどこかで詳しく書きたいなぁ。)
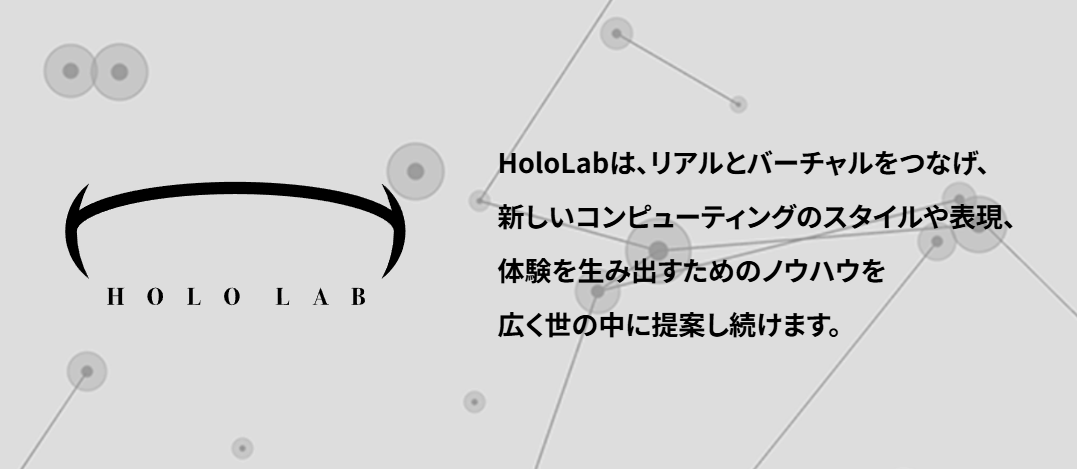
事業
- 売上:約4億円
- インバウンド(問い合わせ/引き合い)やリピートのPoC案件を中心に展開。大規模なシステム開発案件はなし。
- mixpaceなどのプロダクト開発、サービス展開にチャレンジしておりPMF(Prodauct Market Fit)はしていない
XR市場が立ち上がったばかりということもあり、顧客も自社内の研究開発などでPoCが中心の状態でした。それでも日本の大企業(売上TOP20)のほとんどと取引があったのはすごいことです。


組織
- 人数:約30名
- 階層:なし。取締役2名。他にはPM、エンジニア、デザイナー、経理・労務・広報の担当などの役割のみ
- 部門:受託系2部門、プロダクト系1部門(mixpace)、R&D、経営企画など
- 採用:XR界隈の知人や、X(旧Twitter)、リファラルなどで採用
受託事業は顧客ドメインで分けられつつも、中村さん付け、伊藤タケセンさん付けという意味合いも強い組織でした。中村さん自身が社内で言っていた通り経営企画については「伊藤さんに任せきり」でもありました。 また、狭い業界で、コミュニティ発祥で知り合いが多く、且つ取締役2名が旧Twitterでフォロワー数も多かったことあり、比較的知り合い同士で採用ができていたことは特徴の一つだと思います。
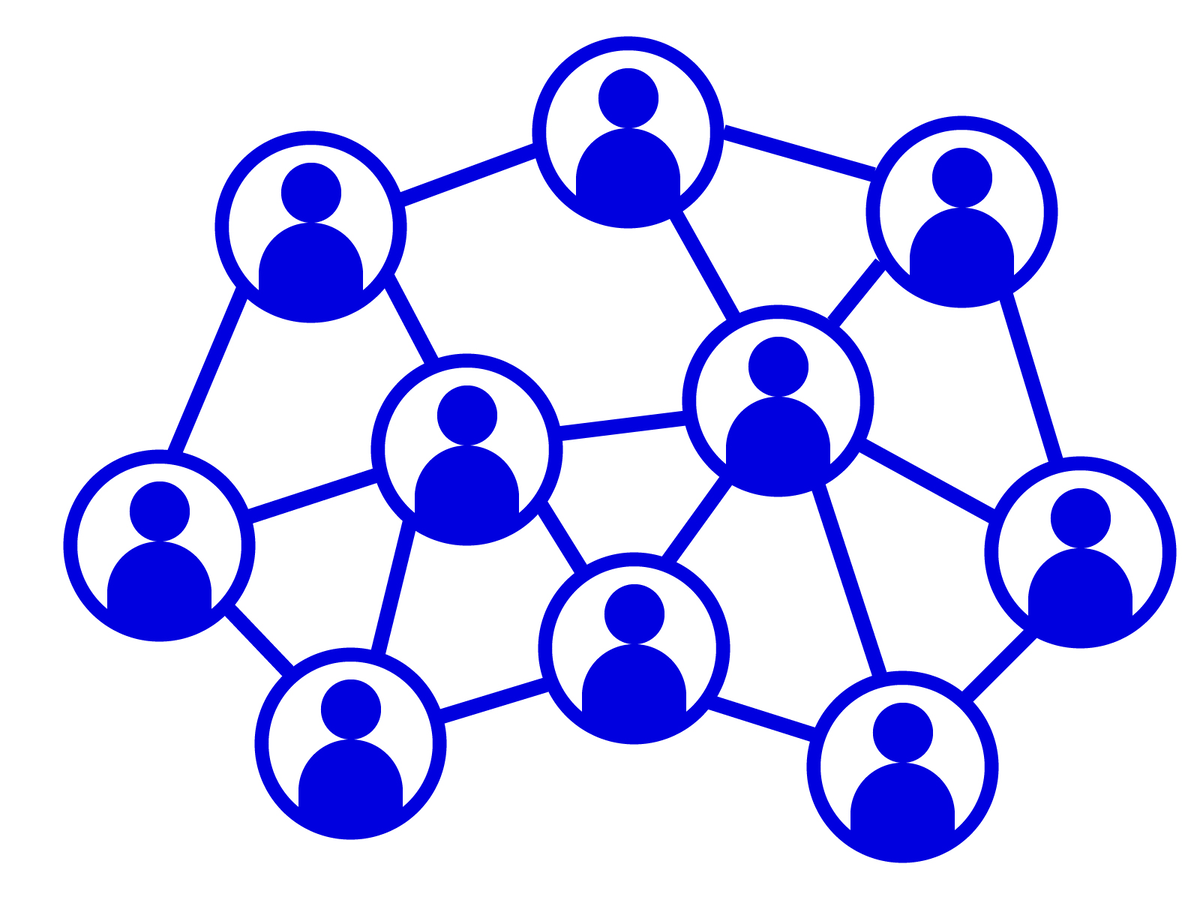
勤務状況
- フルリモート
- 就業時間は設定されているが管理体制はなく、実質運用されていない状態
今でもエンジニアを中心に自宅は全国に広がっており、北海道から福岡まで多様なメンバーが在籍しています。コロナ禍以前からフルリモートで仕事をしていたことがホロラボの大きな特徴です。今後もこの体制を維持するのかどうか、維持するとしてもどういった形態なのかは議論中です。
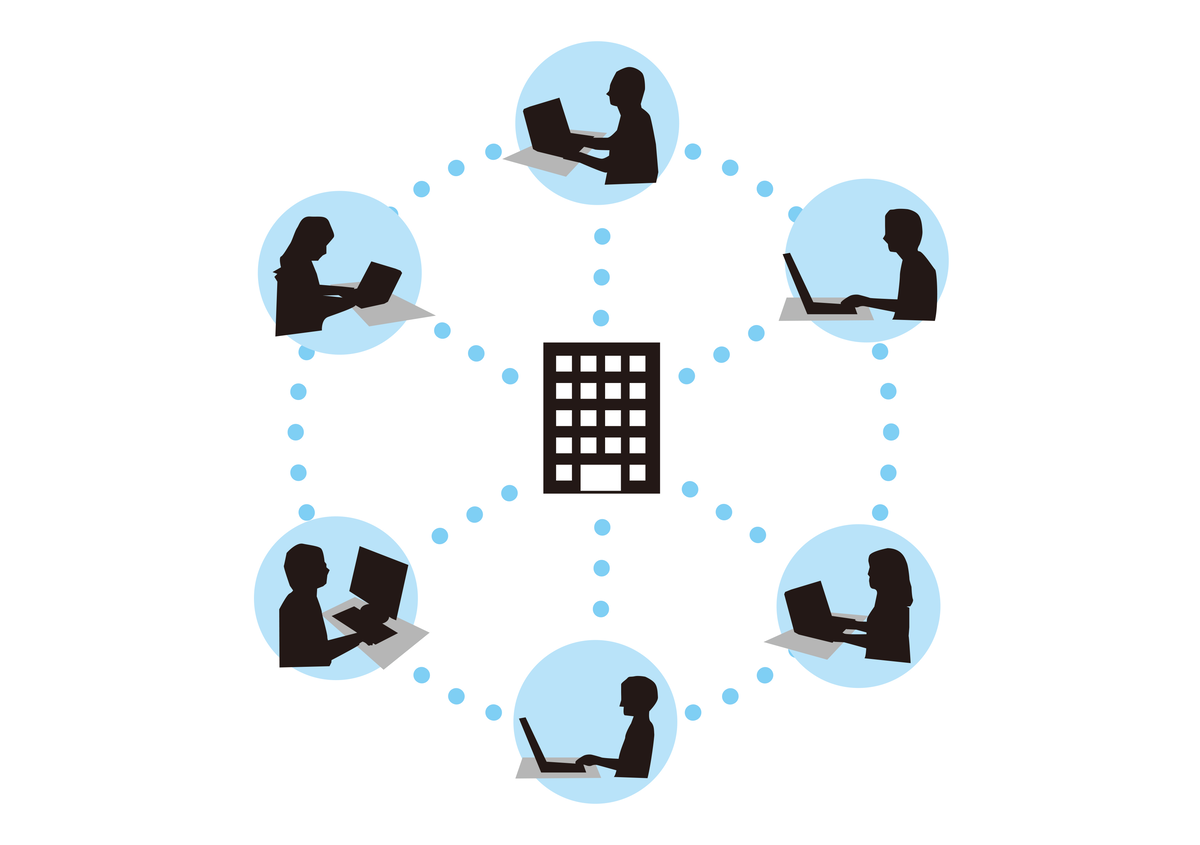
人事考課制度
- 人事考課制度:明文化された規定、制度はなかったが、年に2度の昇給個別面談が設定されていて、申し込むと取締役2名と面談をして、昇給されるかが決まっていた
この昇給個別面談は、取締役2名が「昇給したいなら自分からアピールしてほしい」という考え方に基づいていました。自律性を尊重しつつも、なかなかハードな物言いではあります。w
一方で、考課制度がないため基準が曖昧であり、「アピールしに来たら、なんとなく昇給させなくてはいけない気がする」という取締役の優しさ(?)もその後に問題になってきます。

コミュニケーション
- ツールはSlackが中心。顧客や案件ごとのルームなどがあり、Slackとオンラインミーティングでコミュニケーションを取る
- 各メンバーが自分の部屋(Slackのチャンネル)を持っていて独り言や業務進捗をアップしている
- 階層がないので、業務は指示・命令というよりも取締役からの「依頼」に近いニュアンス

文化:
- エンジニア中心の組織文化
- 業務は指示・命令というよりも取締役からメンバーへの「依頼」というニュアンスが強い
- 自由
「エンジニアにとっていい環境を作りたい」というのが当時の取締役2名の口癖でした。実際、エンジニアの意見は尊重されることが多かったですし、様々なTec企業のエンジニア組織を参考にしていました。
また、最後の「自由」というのを具体的にどう表現するかが難しいのですが、メンバーから頻繁にそういう声は挙がっていたので、そう感じている人が多かったのだと思います。恐らく、ここまでに述べた「階層性がない」「制度・ルールがない」ということが自由さを感じさせる主な要因だったのでしょう。
ちなみに2022年度に行った「ストレスチェック」では平均値50~60と言われる中で、ホロラボは驚異の約80ポイントをたたき出しています(高いほどいい)。

(注:画像は著者の勝手な「自由」のイメージです。)
まとめ
さて、ここまでかなりざっくりと整理してみましたが、いかがでしょうか? このような組織が売上数億円となっているのは不思議ではないでしょうか? 業界が立ち上がったから運よくその波に乗れた、という側面もありますが、XRソフトウェア開発の企業は他にもありホロラボほどの売上にはならず撤退した企業も多くあります。 なぜ、ホロラボは生き残り、売上を伸ばしたのでしょうか?
もうかなり文字量になってきましたので、今日はここでおしまいにします。 次回は、これらの状況を踏まえて、ホロラボの強みは何か?を検証し、そしてどのように組織開発を進めていったのかに徐々に入っていきたいと思います。